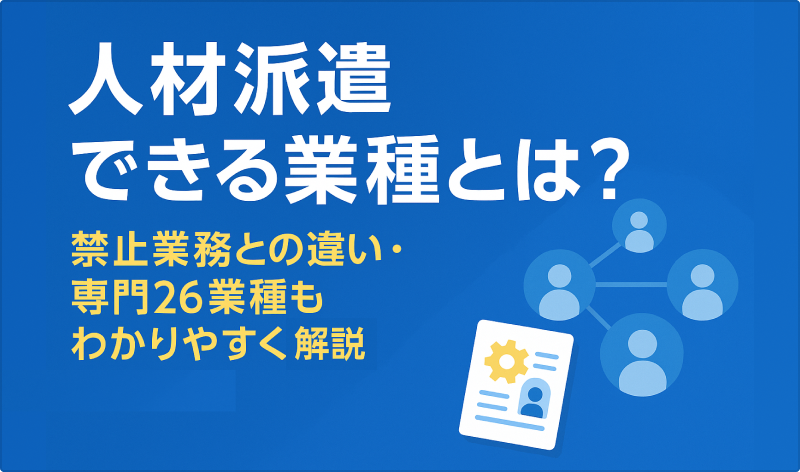人材派遣の導入を検討する企業担当者様が直面する疑問の一つに「自社の業種で人材派遣を利用できるのか」という点があります。この確認は法令遵守の観点から非常に重要です。労働者派遣法では一部の業種で人材派遣の利用を禁止しており正確な知識が求められます。
特に建設業務や医療関連業務などは法律で人材派遣が原則として禁止されている業種です。
本記事では人材派遣ができる業種・できない業種を詳しく解説。法律で禁止されている業務との違いや、かつて存在した専門26業種の正しい知識。どのような業種が派遣を利用すべきかなどの情報をまとめました。
最後までお読みいただくことで自社の課題解決のために人材派遣をどう活用すべきか、その具体的な道筋が見えるはずです。
人材派遣が可能な業種とは
結論からいうと、法律で禁止されている一部の業種を除けば、ほとんどの業種で人材遣は可能です。
現在の労働者派遣法では、派遣を「原則自由」としており、特定の業務のみを例外として禁止しています。そのため、自社で依頼したい仕事が法律で定められた禁止業務に該当しない限り、業種を問わず人材派遣サービスを利用することができます。
ここで重要なのは、派遣の可否が企業の「業種」ではなく、派遣スタッフが実際に行う「業務内容」によって判断されるという点です。例えば、建設業の企業が現場での「建設業務」に派遣スタッフを従事させることは法律で禁止されています。しかし、同じ企業内であっても、事務所での「事務業務」であれば人材派遣を活用することが可能です。
このように、人材派遣を検討する際は自社の業種だけでなく依頼したい業務内容が法的に問題ないかを事前に確認することが不可欠です。
人材派遣が禁止されている業種とは
人材派遣は原則として多くの業務で活用できますが、労働者派遣法により一部の業務では派遣スタッフの受け入れが禁止されています。
これらの禁止業務に派遣スタッフを従事させた場合、法律違反となり派遣先企業も行政指導や改善命令、罰則の対象となる可能性があるため事前の確認が必要です。
禁止業務が定められている背景には、主に労働者の雇用と安全を確保するという目的や、業務の遂行に特別な資格や高度な専門性が求められるといった理由があります。具体的にどのような業務が該当するのか、以下で詳しく見ていきましょう。
法令で禁止されている主な業務とその理由
労働者派遣法では、以下の業務について労働者派遣を原則として禁止しています。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院・診療所などにおける医療関連業務
※例外として以下のような一部のケースでは派遣が認められています。
1.紹介予定派遣の場合
2.育児休業や介護休業などを取得した労働者の代替業務の場合
3.医師の業務で、特にへき地や、地域医療のために派遣が必要と厚生労働省令で定められた場所で行われる場合
また、病院以外の場所(社会福祉施設など)での医療関連業務への派遣は可能です。社会福祉施設では業務が日常の健康管理が中心であり、チーム医療への影響が少ないと考えられるためです。
- 弁護士・社会保険労務士などの「士業」
これらはあくまで特定の「業務内容」にのみ適用され、一般事務など資格が不要な補助的業務については人材派遣の利用が可能です。
禁止されている業務に関して、詳しくは厚生労働省の労働者派遣事業関係業務取扱要領をご確認ください。
人材派遣における「専門26業種」とは
専門26業種とは2015年の法改正まで存在した派遣期間の制限を受けない特別な業務のことで今でも専門性の高い業務を指す言葉として使われることがあるため正しく理解しておくことが重要です。
専門26業種は以下の専門的な知識や技術が求められる26の業務を指していました。
- ソフトウェア開発
- 機械設計
- 事務用機器操作
- 通訳、翻訳、速記
- 秘書
- ファイリング
- 調査
- 財務処理
- 取引文書作成
- デモンストレーション
- 添乗
- 受付・案内
- 研究開発
- 事業の実施体制の 企画、立案
- 書籍等の制作・編集
- 広告デザイン
- OAインストラクション
- セールスエンジニアの 営業、金融商品の営業
参考情報:政令で定める26業務
当時、これら26業務以外の業務には原則として最長3年の期間制限(抵触日)が設けられていました。
専門26業種は代替人材の確保が難しいという特性からこの制限の対象外とされ、企業は期間の上限なく同じ派遣スタッフに業務を任せることが可能でしたが、この制度は派遣労働者の雇用安定の観点から見直され法改正で大きく変更されました。
現在は専門26業種の特例は廃止、全業務に3年ルールを適用
2015年9月30日に施行された労働者派遣法改正により、「専門26業種」という業務の区分と、それに伴う期間制限の特例は完全に撤廃されました。
この改正により、現在ではすべての業務において、派遣の受け入れ期間に原則3年という上限(期間制限)が設けられています。この「3年ルール」には、2つの種類があります。
①事業所単位の期間制限
派遣先の同一の事業所(工場や支店など)が、派遣労働者を受け入れられる期間は、原則として最長3年です。
ただし、この期間制限は事業所の過半数労働組合(または過半数代表者)からの意見聴取を行うことで、3年ごとに延長が可能です。
②個人単位の期間制限
派遣先の同一の事業所における同じ組織単位(部や課など)で、同一の派遣労働者が勤務できる期間は最長3年です。こちらは延長することができません。
個人単位の派遣期間制限である3年が経過する前に、派遣先企業は派遣労働者に対して直接雇用の申し込みを行うなど雇用安定措置を講じる必要があります。
つまり、「専門性の高い業務だから期間制限なく受け入れられる」という考えは、現在は通用しません。同じ派遣スタッフの就業期間が3年に達し、そのポジションで業務を引き続き行う必要がある場合は、まずその方の直接雇用を検討することが求められます。
その上で、直接雇用が難しい場合でも、上記①の手続き(意見聴取)で事業所単位の期間制限を延長していれば、別の派遣スタッフに交代することで、3年を超えても同じポジションで派遣サービスを利用し続けることが可能です。
企業が人材派遣を利用する際のおすすめ業種
人材派遣はさまざまな業種で活用できますが、特にそのメリットを活かしやすいシーンや業種が存在します。ここでは、企業の課題別に4つの代表的なケースと、それぞれに該当する業種の例をご紹介します。
人材確保が困難な業種
各種調査でも人手不足感が深刻とされている介護・福祉、物流、建設、飲食といった業界では、正社員の採用活動だけでは事業に必要な人員を確保できないという課題が深刻です。人材派遣は必要なスキルを持つ人材を迅速に確保できるため、採用市場が厳しい業種においても安定した労働力を確保し、事業を維持・拡大するための有効な一手となります。
一時的な人材不足を解消したい業種
小売業の年末商戦、会計事務所の決算期、イベント関連業界の繁忙期など、時期によって業務量が大きく変動する業種では、人材派遣が最適です。また、業種を問わず、社員の産休・育休や介護休業による長期離脱時の代替要員を確保するといったシーンでも広く活用されています。
採用コストを抑えたい業種
特に、オフィスワークやコールセンター業務などを多くの人員で運営する金融・保険業、情報通信業、サービス業などでは、採用・労務管理の負担軽減を目的として派遣が活用されるケースが多く見られます。派遣を利用すれば、採用工数だけでなく、入社後の社会保険手続きや給与計算といった労務管理の大部分を派遣会社に任せることが可能です。
専門性の高い人材が必要な業種
IT業界、広告・Web制作業界など、高度な専門スキルが求められる業種ではプロジェクト単位で専門職の派遣が活用されています。新規事業の立ち上げや特定のプロジェクトの期間中だけプロフェッショナルの力を借りることで、人件費を固定費ではなく変動費として柔軟にコントロールできます。
typeIT派遣はIT・Web業界に強く、システムエンジニアやプログラマなどの開発領域、ネットワーク・サーバーなどのインフラ領域、WebディレクターやWebデザイナーWebコーダーなどのクリエイティブ領域のスタッフが活躍しています。
業界特有の職種も提案可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
弊社の強みは以下よりご確認いただけます。
まとめ 人材派遣の業種|重要ポイントと活用のコツ
本記事では人材派遣が可能な業種や禁止されている業務、法改正によるルールの変遷、そして企業が派遣を効果的に活用するためのシーンについて解説しました。
最後に、重要なポイントを改めて確認しましょう。
- 派遣の可否は「業種」ではなく「業務内容」で決まる
労働者派遣は、一部の禁止業務を除き、原則としてすべての業種で活用が可能です。ただし、重要なのは企業の業種ではなく、派遣スタッフに依頼する「業務内容」が法律に抵触しないかという点です。
- 禁止業務と例外規定の確認が不可欠
建設業務、警備業務、医療関連業務など、安全や高度な専門性が求められる一部の業務では派遣が禁止されています。一方で、例外的に派遣が認められるケースもあるため、事前の確認が重要です。
- 全業務で「3年ルール」が適用される
2015年の法改正により、かつて存在した「専門26業種」の期間制限の特例は撤廃されました。現在は、どのような業務であっても原則3年という派遣期間の制限(3年ルール)が適用されることを正しく理解しておく必要があります。
人材派遣の制度は複雑に感じるかもしれませんが、そのルールを正しく理解し、自社の課題と照らし合わせることで、経営を支える強力な一手となり得ます。
人手不足の解消、専門スキルの確保、コスト構造の最適化など、自社が抱える課題は何か。どの業種・部署で人材を必要としているのかを明確にした上で、人材派遣の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
具体的な導入計画や法的な側面に不安を感じる場合は、専門知識が豊富な人材派遣会社へ相談することをおすすめします。自社の状況に合わせた最適な活用プランの提案が受けられるでしょう。
本記事では様々な業種における派遣のルールを解説しましたが、特に専門性が高く、人材の流動性が激しいIT・Web業界において課題をお持ちでしたら、業界に特化したtypeIT派遣にぜひご相談ください。
Webディレクター、UI/UXデザイナー、各種エンジニア、Webマーケターなど、業界の最前線で活躍する豊富なIT人材が多数在籍しております。
まずは貴社の事業内容やプロジェクトの課題をお聞かせください。IT・Web業界を熟知したキャリアコーディネーターが、法令を遵守した上で最適なプランをご提案いたします。