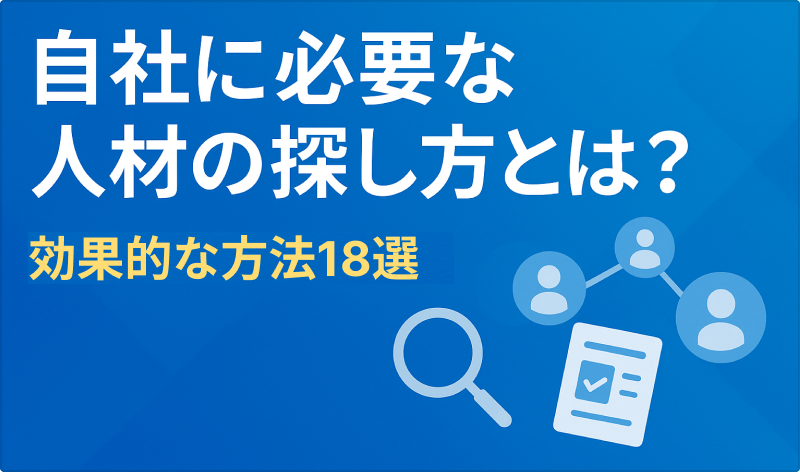企業の成長を左右する人材。しかし人材不足は深刻化しており、2025年4月の帝国データバンクの調査では正社員が「不足」していると感じる企業は51.4%にものぼります。
このような状況下で「どのように自社に必要な人材を見つけ、確保するか」は多くの企業が抱える喫緊の経営課題です。
本記事では、採用活動の基盤となる「自社に最適な人材」の定義方法から派遣サービスを含む多様な人材探しの手法、そして自社に合った方法を選ぶポイントまでを体系的に解説。それぞれの手法の特徴や効果的な活用シーンを整理し、戦略的な採用計画を立てるためのヒントを提供します。
採用活動の質を高め、ミスマッチのない人材確保を目指す方はぜひご一読ください。
自社に必要な人材探しの考え方
効果的な人材探しは具体的な手法を探す前に、自社の採用活動の「軸」を定めることから始まります。ここでは採用の成否を分ける人材像の定義と、人材探しに潜む代表的な課題・リスクについて解説します。
自社に合う人材の定義とは
人材探しを成功させる上で重要なのが自社にとって「必要な人材」がどのような人物か、解像度を高く定義することです。
求めるスキルや経験といった「見える能力」だけでなく、企業理念への共感度、価値観、仕事への姿勢といった「見えにくい特性」が自社の文化や風土にフィットするかどうかが勤務後の活躍と定着の鍵を握ります。
例えば、事業のスピード感を重視する企業であれば、環境変化への柔軟性や即応力を持つ人材が求められます。一方で、新規事業を推進するフェーズでは、既成概念にとらわれないチャレンジ精神や自律性が不可欠です。
自社の事業戦略やビジョンと連動した人物像を「採用ペルソナ」として具体化し、担うべき職務内容や責任範囲を「ジョブディスクリプション(職務記述書)」で明確にすることで採用活動の方向性が定まり、ミスマッチを効果的に防ぐことができます。
人材探しの課題とリスク
人材探しにおけるコストと時間の制約は大きな課題です。
2020年度のデータによると、新卒採用における一人あたりの平均採用コストは90万円を超えており、以降採用活動にかかる費用の見通しとしては同じかそれ以上と回答している割合が高くなっています。
多様な採用手法の中から自社に合わないものを選んでしまうと、想定以上の費用がかかるだけでなく、採用担当者の貴重な時間や労力が奪われ、結果として通常業務にまで支障をきたす恐れがあります。
次に、採用のミスマッチも深刻なリスクとなっています。十分に人物像を定義できないまま採用を進めると、スキルやカルチャーの不一致から早期離職に繋がりかねません。新規学卒者の就職後3年以内の離職率は34%を超えており、企業にとって大きな損失となっています。
働き方の価値観が多様化する中で、旧来の採用活動を続けていると求職者から選ばれにくくなるリスクもあります。これらの課題を踏まえ、場当たり的ではない、戦略的な人材探しが不可欠です。
具体的な人材探しの方法 18選
ここからは、具体的な人材探しの方法について解説します。
まずは自社の状況やニーズに応じて選びやすい派遣サービスについて詳しく紹介し、その後にその他の代表的な方法を簡潔に説明します。
人材派遣サービス
人材派遣サービスは変化する事業環境に迅速に対応しながら、必要なスキルを持つ人材を確保するための有効な手段です。採用市場が激化する中でも多様な職種・スキルを持つ登録者の中から、企業のニーズに合った人材をスピーディーに確保できるため多くの企業で活用されています。
派遣サービスは、主に「有期雇用派遣(登録型派遣)」「無期雇用派遣(常用型派遣)」「紹介予定派遣」の3つの形態に大別され、それぞれに特徴と法律上のルールがあるため、正しく理解して活用することが重要です。
1.有期雇用派遣(登録型派遣)
一般的に「派遣」と聞いてイメージされる最も標準的な形態です。派遣スタッフは派遣会社に登録し、派遣先企業が決まった際に初めて雇用契約を結びます。
- 活用シーン: 繁忙期やプロジェクト単位の業務、産休・育休取得者の代替など、必要な期間が明確な場合に適しています。
- 特徴: 労働者派遣法により、同じ事業所の同じ部署で派遣社員が働ける期間は原則3年までという「期間制限(3年ルール)」が定められています。3年を超えて同じ人材に依頼したい場合は、直接雇用に切り替えるなどの対応が必要です。
2.無期雇用派遣(常用型派遣)
派遣会社の正社員(または契約社員)として無期雇用されているスタッフが、企業に派遣される形態です。
- 活用シーン: 長期的なプロジェクトや、専門性が高く継続的な関与が求められる基幹業務などに適しています。
- 特徴: 派遣会社で安定的に雇用されているため、高いスキルや専門知識を持つ人材が多い傾向にあります。また、有期雇用派遣と異なり「3年ルール」の適用を受けないため、同じ人材に長期間にわたり活躍してもらうことが可能です。
3.紹介予定派遣
派遣期間(最長6ヶ月)の終了後、本人と派遣先企業の双方が合意すれば、直接雇用(正社員や契約社員)に切り替わることを前提としたサービスです。
- 活用シーン: 直接雇用を検討しているが、採用後のミスマッチを避けたい場合に最適です。
- 特徴: 実際に働いてもらいながら、スキルや業務への適性、人柄、自社の文化との相性などをじっくりと見極めることができます。求職者側も企業の雰囲気や仕事内容を理解できるため、双方にとって納得感の高い採用が実現しやすくなります。
これらの派遣サービスを戦略的に活用することで、採用にかかる工数やコストを大幅に削減しつつ、事業に必要な人材を迅速かつ的確に確保することが可能になります。
typeIT派遣はIT・Web業界に強く、システムエンジニアやプログラマなどの開発領域、ネットワーク・サーバーなどのインフラ領域、WebディレクターやWebデザイナーWebコーダーなどのクリエイティブ領域のスタッフが活躍しています。
業界特有の職種も提案可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
エージェント採用
4.人材紹介会社(エージェント)
企業の採用要件(スキル、経験、年収など)を伝え、条件に合う候補者をプロのキャリアアドバイザーが探して紹介してくれるサービスです。
一般的に、採用が決定した時点で費用が発生する「成功報酬型」が多く、採用工数を大幅に削減できる点が魅力です。非公開求人として募集できるため、事業戦略に関わる重要なポジションの採用にも適しています。
5.大学・専門学校との連携
大学のキャリアセンターや就職課、研究室の教授などと関係を構築し、新卒や若手人材の採用に繋げる手法です。
学内説明会やインターンシップを通じて早期から学生と接点を持つことができます。継続的な関係構築が求められますが、毎年安定して優秀な若手人材を確保できる可能性があります。
6.ハローワーク(公共職業安定所)
国が運営する公的な職業紹介機関で無料で求人を掲載できます。
全国各地に拠点があり、地域に根差した採用活動に強いのが特徴です。採用コストを徹底的に抑えたい場合に有効ですが、掲載できる情報量に限りがあり他の手法に比べて専門職や若手層へのアプローチが弱い側面もあります。
広告採用
7.自社採用サイト
企業の理念や事業内容、働く環境の魅力をダイレクトに伝えられるオウンドメディアです。
情報発信の自由度が高く、応募者の情報を自社データとして蓄積できるため中長期的な資産になります。ただし、サイトへの集客施策(SEO対策やWeb広告など)を別途行わなければ応募が集まりにくい場合があります。
8.求人検索エンジン
Indeedや求人ボックスなどインターネット上の求人情報を集約して提供するサイトです。
無料掲載枠とクリック課金制などの有料掲載枠があり、予算に応じて露出度を調整できます。非常に多くの求職者が利用するため幅広い層にアプローチできますが、多数の求人に埋もれやすいため、応募者の目を引くための求人票作成の工夫が求められます。
9.求人広告(Web媒体・紙媒体)
転職サイトなどのWeb媒体や、求人誌・新聞といった紙媒体に広告を掲載する従来型の方法です。
媒体ごとに読者層や得意な職種・地域が異なるため、ターゲットに合わせて選定することが重要です。特に紙媒体は、特定の地域やWebに不慣れな層へのアプローチに有効です。
10.ポスティング
特定の地域の住宅や事業所に求人チラシを直接投函する手法です。パート・アルバイト募集など、勤務地が重要な採用において周辺住民に直接アプローチしたい場合に高い効果を発揮します。
ダイレクト・リファラル採用
11.ダイレクトリクルーティング
企業が人材データベースやSNS等を利用して求める候補者に直接アプローチする「攻め」の採用手法です。
特定のスキルや経験を持つ人材に効率良く接触でき、採用エージェントを介さないためコストの最適化も期待できます。ただし、候補者選定からスカウト文面の作成、面談調整までを自社で行うため運用ノウハウが必要です。
12.リファラル採用(社員紹介)
自社の社員や元社員からその人脈を通じて信頼できる候補者を紹介してもらう手法です。
紹介者によって企業文化や働き方への事前理解が進んでいるためカルチャーフィットしやすく、入社後の定着率向上が期待できます。一方で、人間関係が絡むため不採用時の伝え方に配慮が必要であり、紹介が特定の部署や関係性に偏らないような仕組みづくりも求められます。
13.アルムナイ採用(元社員の再雇用)
一度退職した元社員(アルムナイ)を再び雇用する手法です。
既に企業文化や事業内容を深く理解しているため、即戦力としての活躍が期待でき、ミスマッチのリスクが極めて低い点が大きなメリットです。退職者と良好な関係を維持し、定期的にコミュニケーションを取るネットワークの構築が成功の鍵となります。
14.SNS採用(ソーシャルリクルーティング)
X(旧Twitter)やLinkedIn、FacebookなどのSNSを活用する採用手法です。
自社の魅力や社風を日常的に発信することでまだ転職を具体的に考えていない「潜在層」にもアプローチできます。企業のブランディングにも繋がりますが、継続的な情報発信が不可欠であり、不適切な発信による炎上リスクの管理も必要です。
イベント採用
15.転職フェア・合同説明会
多様な業界・企業が一堂に会し、多くの求職者と直接対話できるイベントです。
企業の認知度向上やWebサイトだけでは伝わらない社内の雰囲気などを直接伝えられる良い機会になります。多くの求職者と会える一方、競合他社も多数出展しているため自社ブースに興味を持ってもらうための工夫が必要です。
16.オンライン説明会
遠方に住んでいる、あるいは現職が多忙で時間を確保しにくい求職者でも参加しやすいのが最大のメリットです。
会場費も不要で企業・求職者双方の負担を軽減できます。一方で、対面と比べて企業の雰囲気や細かいニュアンスが伝わりにくい場合があるため、コミュニケーションの取り方に工夫が求められます。
17.ミートアップ・カジュアル面談
選考とは切り離し、リラックスした雰囲気で求職者と交流する場です。
企業説明会よりも双方向のコミュニケーションが取りやすく、候補者の素顔や価値観に触れながら自社への興味を高めてもらうことができます。転職潜在層へのアピールや本格的な選考に進む前の相互理解の深化に有効です。
その他
18.採用広報・動画活用
社員インタビューやオフィス紹介、企業理念を伝える動画コンテンツなどを制作し、自社採用サイト等で発信する活動です。
視覚的に企業の魅力を伝えることで、候補者の共感や応募意欲を高めます。単体で行うよりも、SNS採用など他の採用手法と組み合わせることで効果を最大化できます。
自社に合った人材探しの方法を選ぶポイント
数多くの採用手法の中から自社に最適なものを選ぶには、明確な「判断軸」を持つことが不可欠です。
ここでは、採用の成否を分ける3つの重要なポイント、「①求める人材と緊急度」「②コストと投資対効果」「③自社の採用リソース」について解説します。
① 求める人材(即戦力/ポテンシャル)と緊急度で選ぶ
まず考えるべきは「いつまでに、どのような人材が必要か」という採用の根本的な要件です。
-
即戦力人材を、スピーディーに確保したい場合
欠員補充や事業拡大などで専門スキルを持つ人材を迅速に確保する必要があるなら、人材紹介や派遣サービスが非常に有効です。
また、求めるスキルセットが明確であれば、候補者を直接探せるダイレクトリクルーティングもスピーディーな採用に繋がります。
-
カルチャーフィットを重視し、時間をかけて育成したい場合
自社の文化や価値観に深く共感し、長期的に会社と共に成長してくれるポテンシャル人材を求めるなら、リファラル採用や自社採用サイトでの丁寧な情報発信が効果的です。
新卒採用を目的とするなら、大学・専門学校との連携も選択肢となるでしょう。
② 採用コストと投資対効果(ROI)で選ぶ
採用コストは目先の金額だけでなく、長期的な視点で捉えることが重要です。コストは大きく2種類に分けられます。
-
外部コスト
求人広告の掲載費、人材紹介会社への成功報酬、採用ツールの利用料など、社外へ支払う費用。
-
内部コスト
採用担当者の人件費、面接官の時間、研修費用など、社内で発生する費用。
例えば無料のハローワークは外部コストを抑えられますが、応募者対応などで内部コストが増加する可能性があります。逆に手数料がかかる人材紹介は候補者の厳選や面談調整を代行してくれるため、内部コストを大幅に削減できます。
最も避けたいのは、採用のミスマッチによる早期離職です。一人の早期離職者が出ると、それまでにかかった採用コストと教育コストが無駄になります。
表面的な安さで手法を選ぶのではなく、「採用ROI(投資対効果)」の視点を持ち、長期的に企業の成長に貢献してくれる人材を確保できる手法を選ぶことが、結果的に最もコスト効率の良い選択となります。
③ 自社の採用リソース(体制・ノウハウ)で選ぶ
どれほど優れた採用手法も、それを使いこなす社内体制がなければ期待する成果は得られません。
-
採用チームが少人数、または担当者が多忙な場合
採用活動に多くの工数を割けないのであれば、候補者の選定から日程調整までを外部に委託できる人材紹介や派遣サービスが適しています。
求人広告も一度出稿すれば応募を待つスタイルなので、比較的少ない労力で始められます。
-
採用ノウハウを社内に蓄積し、専門チームで取り組める場合
採用活動に主体的に関わり、将来的な資産としてノウハウを蓄積したい企業には、ダイレクトリクルーティングや自社採用サイトの強化がおすすめです。候補者との直接のやり取りを通じて、自社が求める人材への解像度が高まり、採用ブランディングの強化にも繋がります。
| こんな企業におすすめ | 主な採用手法 | メリット |
| 【緊急度:高】 即戦力をすぐに確保したい |
・人材紹介 ・派遣サービス ・ダイレクトリクルーティング |
スピーディーな採用が可能。求めるスキルを持つ人材に直接アプローチできる。 |
| 【育成重視】 カルチャーフィットする人材をじっくり育てたい |
・自社採用サイト ・リファラル採用 ・大学/専門学校連携 |
企業理念への共感度が高い人材を採用しやすい。定着率向上が期待できる。 |
| 【リソース:少】 採用担当者の工数を削減したい |
・人材紹介 ・派遣サービス ・求人広告 |
候補者選定や調整を外部に委託できる。比較的少ない労力で始められる。 |
| 【ノウハウ蓄積】 採用力を自社の資産にしたい |
・ダイレクトリクルーティング ・自社採用サイト強化 ・リファラル採用 |
採用ノウハウが社内に蓄積される。採用ブランディングに繋がる。 |
成功する人材探しの実践ポイント
最適な採用手法を選んだとしても、候補者とのコミュニケーションや入社後のフォローが不十分では人材探しは成功に至りません。ここでは、採用活動の成果を最大化するための具体的な実践ポイントを紹介します。
ただし、これらの取り組みは専門的なノウハウと丁寧な対応が求められます。自社のリソースで実践が難しい場合は、派遣等外部サービスの活用も視野に入れることが成功の近道です。
求人メッセージと面談の工夫で「候補者体験」を高める
現代の採用は、企業が候補者を選ぶだけでなく、候補者から「選ばれる」時代です。そのため、応募から選考、内定に至るまでの一貫した候補者体験の質を高める視点が不可欠です。
求人メッセージの工夫
候補者が最も知りたいのは入社後のリアルな姿です。具体的な仕事内容、期待する役割、キャリアパスはもちろん、仕事のやりがいや魅力といったポジティブな側面と、大変な点や乗り越えるべき課題といったネガティブな側面の両方を正直に伝えることで候補者の信頼を高め入社後のミスマッチを防ぎます。
面談の工夫
面談は候補者を「見極める」だけの場ではありません。
自社の魅力を伝え、候補者の入社意欲を高める「魅力づけ」の場でもあります。ただし、候補者一人ひとりへのこうした丁寧な対応は質の高い採用に繋がる一方で、採用担当者の大きな負担にもなります。
採用後の「オンボーディング」で定着と活躍を支援する
採用活動は内定や入社がゴールではありません。採用した人材が組織にスムーズに溶け込み、早期にパフォーマンスを発揮できるよう支援するオンボーディングの取り組みがポイントです。
新入社員は、新しい環境や人間関係、業務内容に対して、期待と共に大きな不安を抱えています。この初期段階での不安を放置してしまうと、組織への孤立感やエンゲージメントの低下を招き、最悪の場合、早期離職に繋がってしまいます。
丁寧な初期フォローが、定着と活躍の分かれ道になると言っても過言ではありません。
具体的な施策としては、以下のようなものが挙げられます。
- 入社前のコミュニケーション(内定者フォロー)
- 部署メンバーとの顔合わせやランチ会の設定
- 業務に必要な知識やスキルを学ぶ研修
- 気軽に相談できる先輩社員(メンター)の配置
- 上司との定期的な1on1ミーティング
とはいえ、これらのオンボーディング体制を自社だけで完璧に整備・運用するには相応の体制が必要です。
そこで有効なのが、紹介予定派遣の活用です。直接雇用を前提としながらも派遣期間(最長6ヶ月)が実質的な「双方にとってのお試し期間」となり、効果的なオンボーディングとして機能します。
実際の業務を通じてスキルやカルチャーフィットを見極めながら、スムーズに組織の一員として迎え入れる準備ができるため、入社後の定着と早期活躍に繋がりやすくなります。
まとめ IT人材をお探しならtype IT派遣にご相談ください
本記事では、効果的な人材探しの「考え方」から、派遣サービスを含む多様な手法、自社に合った選び方のポイント、そして成功のための実践ポイントまでを体系的に解説しました。
成功する人材探しは、単に手法を試すことではありません。まず①自社に必要な人物像を明確に定義し、次に②事業の状況や採用リソースに合わせて最適な手法を組み合わせ、そして③採用後も定着・活躍までを見据えてオンボーディングを行うという、一貫した戦略が不可欠です。
特に、事業の成長スピードを落とさずに即戦力を確保したい場合や採用のミスマッチを避けたいと考えるなら派遣の活用は非常に有効的な解決策となり得ます。
本記事では、効果的な人材探しの考え方から具体的な手法までを網羅的に解説しました。しかし、数ある選択肢の中から自社に最適な手法を選び、採用を成功に導くのは決して容易ではありません。
特に、変化の速いIT・Web業界では事業の成長を止めないためにも専門スキルを持つ人材を迅速に確保することが企業の競争力を大きく左右します。
「結局どの採用手法が自社に一番合っているのか分からない」
「IT・Webに特化した即戦力人材をスピーディーに見つけたい」
「採用のミスマッチは避けたい見極めるための工数やノウハウがない」
「採用活動に時間を取られず本来のコア業務に集中したい」
このような課題をお持ちでしたら、IT・Web業界専門のtypeIT派遣にぜひご相談ください。
貴社の具体的な採用課題や求めるスキルを丁寧にヒアリングし、豊富なIT人材の中から最適な方をご提案可能です。職種やスキルレベルごとの料金相場を熟知したキャリアコーディネーターが、貴社に最適な人材をご提案いたします。